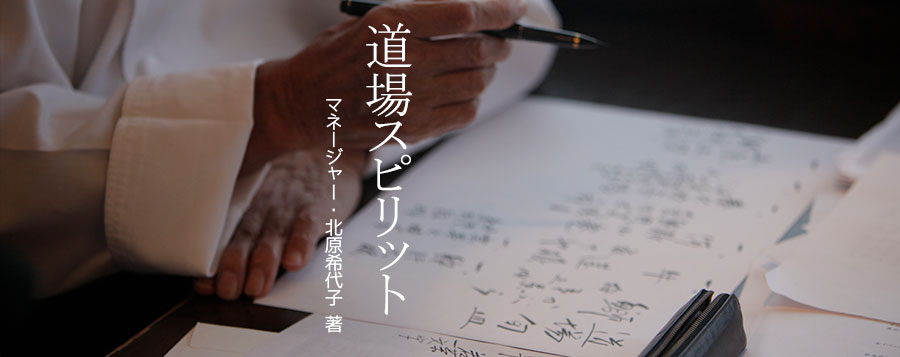
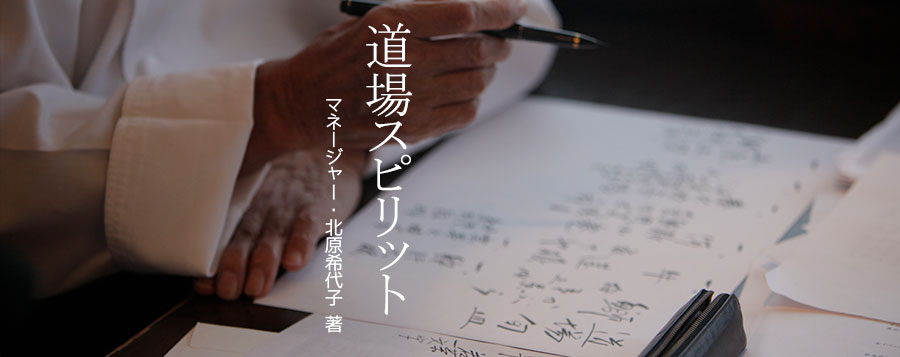
#3忘れられない師匠との出会い
杉本成次朗先生、柳井福一先生、井垣圭弘先生、そして茶道の師匠、数江瓢鮎子先生。
道場にはその時代時代で忘れることのできない大師匠がいる。
杉本成次朗先生は、神戸時代、六甲花壇の頃に、道場が最も強い影響を受けた師匠の一人だ。道場の代名詞になっているお品書きも、杉本先生の筆文字に倣って始めたこと。ものを大きく捉え創意工夫にあふれた献立の発想は、料理だけでなく器や書画骨董にも造詣は及び求めてそうした出会いの時間を大切にしたと言う。だから、献立の書き方も他人とは違う、「席入り・床横山大観・富士」と床の間の軸にまで心を配り、前菜なども「小八寸」と書いたり「酒菜」と書いたりと、その席その席に合った書き方をした。
芝居好きで、「敵八方より来る、我に八方の構えあり」と、新国劇を真似ては決まり文句「サブちゃん、脇が甘いよ。隙がある、隙が!」とよく注意されたと、先日もある雑誌のインタビューのとき道場が懐かしそうに話していた。俎板前を美しく、布巾の洗い方から畳み方にまで気を配って、常にお客様に見られているのだと言うことを無言で教えてくれた師匠だった。
柳井福一先生とは、好景気に沸いていた昭和二十九年、東京の芝浦「ぼたん」に煮方として呼んでもらったのが、師弟関係の始まりだった。「思えば柳井先生がこの道を繋いでくれたんだよなぁー」と、道場は懐かしそうに思い出していたが、料理人としての第一歩を踏み出した「くろかべ」から神戸六甲への道を付けてくれたのも全て、大京会の前身である日本料理研究会で師範をしていた柳井先生だった。
芝浦と言えば、東海道線と東京湾に鋏まれた埋立地、日の出桟橋があり、魚の料理には縁が深い。「ぼたん」は、ちょうど芝浦の真ん中辺り、当時としてはかなり洒落た店で、芸者衆を連れた二次会の客が多かった。道場はこの頃ふぐの免許を取り、煮方として充実した日々を送っていた。仕事に関するいろいろな興味も出て来て、日々の疑問や、新しい課題などノートに書いては、根津の師匠の家を訪ねた。殆ど毎週のように一升提げてやって来る道場を、柳井先生は面倒がらず優しく指導してくれたと言う。
「あの頃の私は、料理が面白くて仕方なかった」と、後に道場も語っているが、三つの地域(関西・北陸・東京)を渡り歩いて身につけた、道場の料理。道場和食を開花させる土台を作ってくれた大事な出会いだった。
柳井福一先生とは、もう一つ不思議な縁に彩られている。二〇〇〇年にオープンした懐食みちばの料理長柳井一成さんは福一先生の孫。彼もまた、二十八歳の若さでろくさん亭の料理長を務め、道場の懐刀として、懐食みちばのオープンを支えた一人だ。福一先生の息子武さんもまた料理人、親子三代、武さんが大学出たての一成さんを連れて道場のもとを訪ねたのはもう三十年近くも前のことだ。
昭和三十一年、関西調理師大京会に赤坂常磐家への入込み話が来た。当時、会の会長を務めていた井垣圭弘先生に付いて道場も赤坂常磐家のフグ場に付かせて貰うことになった。赤坂の田町にあった常磐家は、大勢の政治家たちが出入りする料亭政治の表舞台だった。毎夜、黒塗りの車がずらりと並んで、夜になっても人は減らない。調理場の人数は七~八人、お客さんが十人位までなら一人仕事。二十人なら二人、三十人なら三人とだいたい決まっていた。時たま、総理官邸への出張料理もあり、外務省関係のお客様も多かったので、外人も必然的に多かったと言う。
井垣先生は京都の人なので、湯葉や麩の仕事が得意だった。どちらかと言うと古いタイプの職人だったが、よく本当に面倒をみてくれた。月に一回ほど食に興味のある人を中心にした「常磐会」という、新しい料理の愛好会もあって、皆で食べては講評し合う刺激的な時間も持てた。後に、天皇の料理番で有名に成った秋山徳三さんなどもよくこの会に顔をみせた。まだクーラーもない時代、庭に井戸を掘って水を屋根に上げ、竹筒に穴を通して夕立を降らせたり、座敷に氷柱を置いて涼をとったりと、お客様を喜ばせる術や工夫もこの店で勉強した。
昭和三十四年、料理長だった井垣先生が他へ移ることになり、なぜか料理長の椅子が道場に回って来た。常磐家のような大店で若干二十九歳の若者が料理長に成るなど考えられないことだ。周りからの批判も沢山有ったようだが、険しければ険しいほど、道場は燃えるタイプだ。勿論、それだけの実力もあったのだが、何よりも裏表のない人懐こい性格が周りの人を引き付け道場を盛り立ててくれた。こうした支えは、上ばかりとは限らないのだ。同僚は基より、仲居さん達にも慕われていた道場六三郎。周りに好かれてこそ!人の信用というものはそうしたものだと、私自身も道場の傍で勉強させてもらっている。