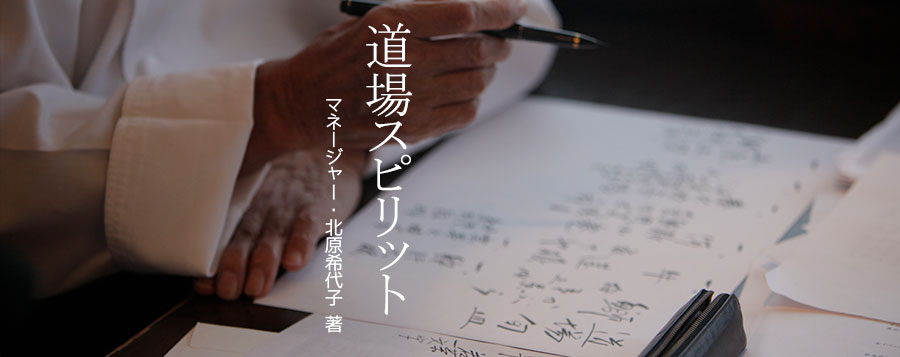
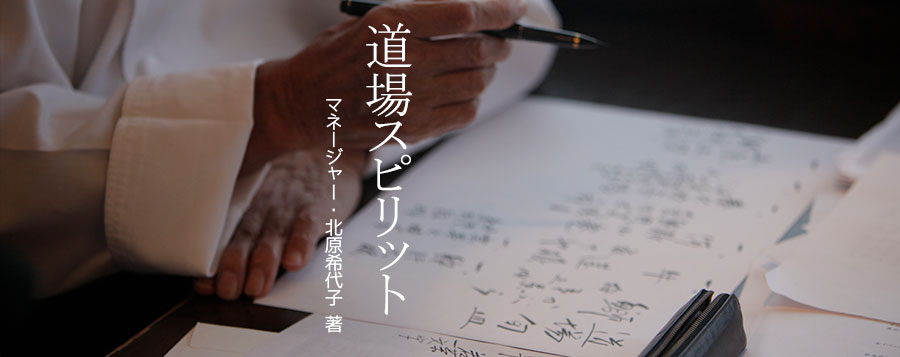
#1プロローグ
道場六三郎八十七歳、日本を代表する料理人である。
十九歳の時に料理人を志し、故郷山中温泉から上京する。
北陸は関西に近く、誰もが関西を目指すところ、道場はなぜか花の東京を選んだ。当時流行っていた「東京ブギウギ」に心が動いたからだ。
道場に取って、この心が動くというワクワク感こそが全ての指針になっているように思う。十三歳の頃に、故郷白山神社に相撲の巡業がやって来た。娯楽の少ない田舎では「双葉山が来るぞ!」とお祭り騒ぎだった。そこで道場少年は閃いた!友達を誘い金沢でリンゴを仕入れて一個五銭で会場で売り捌いたのだ。リンゴは思いのほか良く売れ利益も生んだが、土地の地回りにこっ酷く脅かされ、怖い思いを味わうとともに、商売の仕組みを叩きこまれた。
兄たちは戦地に赴き、生活の一端を担わなければならなくなった道場少年は、やがて金沢や氷見など闇の魚を仕入れては、温泉街の旅館で売り捌く「かつぎや」へと成長して行く。
初めてリンゴを売った時の何とも言えないワクワク感と、「かつぎや」での商売の駆け引きが、後の道場六三郎を作り上げて行った。
六人兄弟の末の三男として生まれた道場少年、土地の方言で「だんくら」と言われるほど、やんちゃな少年だった。何にでも興味を持ち、ときには通学の道すがらワクワクに出会うと何もかも忘れてしまう、別名「みちくさ六三郎」。ジョージワシントンの伝記に触発され、教室の窓ガラスを割った犯人に名乗り出て、先生に酷く叱られたり、教室が殺風景だという先生の言葉に、黒板の回りを杉の枝で飾りクリスマスを気取った時も、待っていたのは先生のゲンコツだった。
酒好きの父の使いで、よく徳利を持って酒を買いにやらされた道場少年。途中の神社でよく味見と称して盗み酒をした。その時の感想は「なかなか旨い!」好奇心旺盛な少年は六歳にして酒の味を覚えた。
酒の師である父親は、同時に料理の師でもあった。道場六三郎の五感を刺激した料理との出会いは、父の造る酒の肴、そして母の作る懐かしいおふくろの味が原点である。漆塗の職人であった道場の父は、山中温泉で棗など茶道具を扱う漆器の工房を営んでいた。仕事の合い間をみては酒の肴をよく作ったという。イワシを糠付けにした「こんかいわし」時には河豚なども捌いて糠漬けにした。寒鮒を背ごしに薄く切って酢の物で食べる「鮒のそろばん」など、末っ子の六三郎は、よくご相伴に預かった。もとより六歳から酒の味を覚えた少年である、父の造る酒の肴にも大いに刺激を受けた。
家業の工房では、学校へ行く前の朝の日課のように、本塗りに入る前の木地固めの素地塗りなど、子ども達はよく手伝ったという。ところが、道場はこの座り仕事が大嫌いだった。何よりも埃を嫌う漆の工房で、静かに座って手を動かすだけの仕事は、やんちゃな少年にとって苦行のように思えた。
道場は一言で言うと、ありとあらゆる側面を持った超人である。
料理を愛する料理人でありながら、同時に超一流の商売人でもある。
道場の目指す料理はただで振る舞う料理ではなく、きちっと利益を生む料理である。だから何時でも食べてくれるお客様を意識している。誤解を恐れずに云えば、お客様が代金を支払うに相応しい料理かどうか。道場の頭の中には、いつでもそれがあるのだと思う。
自分が精一杯作った料理をお客様が喜んで食べてくれる。本当に嬉しいことだが、道場はそれだけでは満足しない。お客様を喜ばせた上に、自分も儲かる。持って生まれたこの商売人気質が自らのワクワク感を増幅させて、また、新しい料理を生み出す原動力になっている。
常に新しいものを求めながら、道場は、大切な昔も傍に置いて同居させている。料理は、「行きつ戻りつ」、道場がよく使う言葉だが、先に進み過ぎるとお客様を置き去りにして自分善がりになってしまう「その頃あいが難しいんだ」と。
此れまで培った六十八年の料理人生、沢山の引き出しの中には有りとあらゆる料理のノウハウが詰まっている。その引き出しの多さは想像を超えるが、道場の凄いところは、引き出しを開けて出された料理やアイデアは、必ず新しい形で引き出しに戻されると言うことだ。
道場の引き出しは、絶えず新しく更新し続けているのである。